第16話 幻の滝 富山市片掛
祖母は、いろりで小豆を煮ながら、この地にまつわる昔話をしてくれた。
昔、昔の、その昔、神通川という名も、立山という呼び名もなく、片掛という地名などついていなかった遠い昔のことである。

片掛一帯に大きな湖があって、長さ南北七里(二十八キロメートル)もあった。もちろん、湖の名も、湖水から落下していたという、高さ三百メートルにもおよぶ大きな滝のことも、今では知る人もなく、この話を伝えるのも、私が最後になるかもしれない。
原住民と呼ぶか、先住民と呼ぶかは、その道の専門家にまかせるとして、とにかく、わずかだが、人はすんでいた。山があって湖があり、せまいとはいえ、平地に近い傾斜地もあり、よい飲み水もあったし、洞穴までもあったのだ。無理に農耕しなくても、わずかな人数なら、生きていくのに、大きな心配をせずにすんだのである。
峠の雪もすっかり消え、若葉が山々をおおい、その緑の中に、山つつじの花がちらほら見える、うららかな春のある日のことである。このあたりでは見かけない、年の頃なら十七、八といった娘がただ一人、下流の方から神通川沿いに、上流の方へ歩いて行った。いつまでに、どこまでたどりつくというあてもなく、話し合う友だちもいないその娘は、ただ黙々と歩き続けていた。
庵谷(片掛の北隣村)までたどり着いた時、はじめは気のせいかと思っていた音が、歩くにしたがって、しだいに大きくなり、ついには、轟々と鳴り響く音だけが、耳に入るようになった。それが、滝の音であることを知らない娘は、その音にひかれ、ひとりでに足が滝の方に向い、遠回りするように進んで行った。
しかし、道などあるわけはなく、庵谷峠の山は、行く手に立ちはだかるような形でさえぎり、山は、さらに,けわしさを増していた。さすがの娘も、しだいに疲れを覚えてきたが、適当な休憩場所はなく、おまけに、山あいの太陽は西に傾いて行った。
進むにつれて、音は大きく聞こえてくるが、すかして見ても、伸び上がって見ても、木の葉がじゃまになって何も見えなかった。
「もっと近くへ行って見よう!」娘は、歩きながら、大きく息をして背のびをしたその時・・・「見えた! 見えた!」 大きな滝が見えたのだ。娘は、これまでに、このように水量が多くて、こんなに高い滝を見たことがなかった。娘は、滝のあまりの見事さに、疲れも何もかも忘れて、ただただ、眺めるばかりであった。

その頃、飛騨の山々の雪解け水が集まった神通川は、いつもより水量が多く、滝の音は木々の枝をゆすり、滝つぼから湧き上がる水煙は、あたり一面に立ちこめていた。
その時である。滝に気を取られていた娘は、足をすべらせ、そのショックで木の枝から手を離してしまい、崖をすべり落ちたのだ。しかし、幸いにも、転落する途中で、身体が木の幹にひっかかり、一命だけは、とりとめたのだが、打ちどころが悪かったのか、虫の息になってしまった。
こんな所を通る人もいないその頃のことである。このまま放置しておけば、当然、その夜のうちに、若い命は、消えたにちがいない。滝は、そんなことを知らないかのように、前と同じ音を立て、同じ響きで落ちていた。
しばらくして、一ぴきの猿が、その娘に近づいてきた。猿は、娘の様子をじっと見ていたが、娘は、全然動かない。それで、猿はさらに近づき、おそるおそる娘に触れてみると、娘は、ぐったりしているけれども、まだ体温はあるし、呼吸もしていることを知った。やがて、その猿は、仲間に知らせるために、その場から離れて行った。

しばらくして、子猿も含めて二十ぴきほどの仲間が集まり、何か相談している様子だったが、「とにかく、娘を助けよう」と、話が決まったようである。
ところが、助けようにも、そこでは水煙にぬれてしまう。どうしても峠の頂上付近まで、運び上げなければならないことは、猿たちにも分かっていたようだ。しかし、日が暮れかかるけわしい山の中では、全員の力を集めても、運び上げる作業は、そう簡単なものではなかった。娘の身体を持ち上げる者、押し上げる者、引き上げる者など、いろいろ試しているうちに、猿たちの力が合わさり始めた。そして、やっとのこと、猿たちの協力は、実を結び、日が暮れる頃には、ついに頂上まで、運び上げることに成功したのだった。
山の上とはいえ、そこには、少し平らで、風当たりの弱い場所があり、猿たちは、娘をそこまで運んだ。しかし、悪いことに、先ほどより、娘の体温がだんだん下がっていることに、猿たちは気がついた。それで、気温が低下してゆく中、一団の猿たちは、娘の体温を温め、別団の猿たちは、食べものの木の芽などを取りに散ったのだった。それから三十分もたった頃だろうか、娘は、かすかに目を開いた。あたりは、すっかり暗くなっているし、まだ、疲れていたので、娘は、再びねむってしまった。しかし、幸いにも、その夜は雨が降らなかったのだった。
朝になって、娘は、目を覚ました。実に、すがすがしい朝だった。娘は起き上がってあたりを見まわした。娘は、自分をいろいろ介抱してくれたのは、人間ではなく猿たちであることが分かったが、人の言葉が通じない猿に、何を言ったらよいのか、お礼の言い方に困っていた。 猿たちは、元気をとり戻した娘を見て、喜んでいる様子で、「キャッ キャッ」と、あたりを走りまわっていた。娘は、猿が集めてきた木の芽などを、少し食べてみた。何の木の芽か分からないが、猿が持って来たのだから毒ではないようだ。少し食べても、身体に異常がないので、娘は安心して食べた。
木の葉の間から見下すと、そこに、大きな湖があることに、娘は気がついた。よくよく見ると、湖面が、春の陽光を反射して、キラキラ輝いている。そして、その中に、水鳥が浮かんだり、飛びまわったりしていた。瞳をこらすと、湖面は、はるかに続き、果ては山の影にかくれて、どこまでが湖か分からないまま、もやに包まれていた。
娘は、これからのことを考えた。山の上では、水にも困るし、雨露もしのげない。どうしても、雨や風に耐えられる所で、水の出る場所を探したい。娘は、そう思いたったらじっとしておられず、少しずつ、南側へ下り、西の方へ歩き出した。猿たちも一緒について歩いたり、木の枝から枝へとび移ったり、一部の猿たちは、食べ物探しにも出かけた。歩くといっても、もちろん道があるわけではない。歩き始めてから、どれほどの時間がたっただろうか。疲れたし、おなかもすいたので、岩の上に腰を下ろし、休憩することにした。
しばらく、ひと休みをして、娘は、また歩きだそうと立ち上がり、あたりを見まわすと、岩肌の向こうに何か黒く見える所を見つけた。「何だろう」と近づきよくよく見ると、それは洞穴だった。「これは天の助け」とばかり、娘は、太陽に両手をあわせて拝んだ。そして、その洞穴に入って行った。

穴の広さは、八畳敷ぐらいで、十分な広さがある。とりあえず、娘は、その洞穴で寝起きすることにした。猿たちは、友だちになってくれ、食べ物も運んでくれるのだ。しかも、眼下が、広々とした湖畔である。娘は、当分の間、ここでゆっくりすることに決めた。
季節は、まだ暖かかったので、着るものは心配なかった。娘は、冬に備えて、藤づるを叩いて、繊維らしいものをたくわえ始めた。この村には(村というほどのものではないが)わずかの「人」が、別の洞穴に住んでいるようだったが、どちらも近よろうとはしなかった。娘は猿たちを友として暮らしているうちに、弓を作ったが、使うこともなかった。それは、木の芽や食べられる草のほか、幸いにも湖の浅いところに貝が多かったので、貝をとって食べていたからだ。
いつもの年なら、梅雨時期には雨の降る日が多いのに、その年は、梅雨の季節になっても雨は少なく、周囲の山々は濃い緑におおわれて、やがて夏が来た。
蝉のなき声が耳に痛いほど聞こえる湖畔である。娘は、毎日のように湖水で汗を流した。洞穴は涼しく、夜はしのぎ易く、虫の音楽もすばらしかった。山では、猿も狐も狸もイタチもテンも、仲よく、暮らしていた。また、熊も人も他のけものたちも、動物たちを襲うようなことはなかった。湖の水は、深い所まで澄んでいて、貝や魚などもよく見えるほどきれいで、空はぬけるような青さだった。

ある日のこと、入道雲がしだいに鉛色となり、その動きも激しくなって、気温が急に下がり、風が吹きはじめたのだ。突然の天変異変に驚いた猿たちは、空を見上げてただ泣くばかりである。しかも、猿たちの動きは、今までに見たことのないものだった。娘は、いやな予感がしたが、見守るばかりだった。と、その時、大粒の雨が降り出した。
はじめ弱かった風もしだいに強くなり、雨はますますはげしくなって、湖水を隔てた向うの山が見えなくなった。そのうち、谷という谷、川という川のすべてが鉄砲水となって、濁流が音をたててあふれるほどになって来た。青く「静」そのものに見えた湖面も、流れ込む川のあたりから褐色に変わって行き、ついには濁流が渦巻くようになってきた。
強い風とはげしい雨のために、あちこちの枝になっていた木の実が振落とされて、すぐに濁流にのみこまれて流れて行った。
これを見た猿たちは、泣き叫んでいる。それは、悲鳴にも似たもので、直接、生命にかかわる重大事ということを知っているのか、空を見上げたり、木の実を眺めたりして、悲しみと驚きを顔にあらわしていた。
風は、やがて弱くなったものの、雨は、なかなか止まなかった。濁流は、大きな木を根こそぎ抜きとって流していき、山から押し出された土砂は、小さな谷を埋めてしまった。次から次へと流れてくる大木が、湖で渦を巻いている。その木の枝に、小さな動物がしがみついているのが見える。しまいには、山津波が起き、直径数十メートルもの岩までも流され転がり、この世の終わりかと思えるほどの、すごさになった。
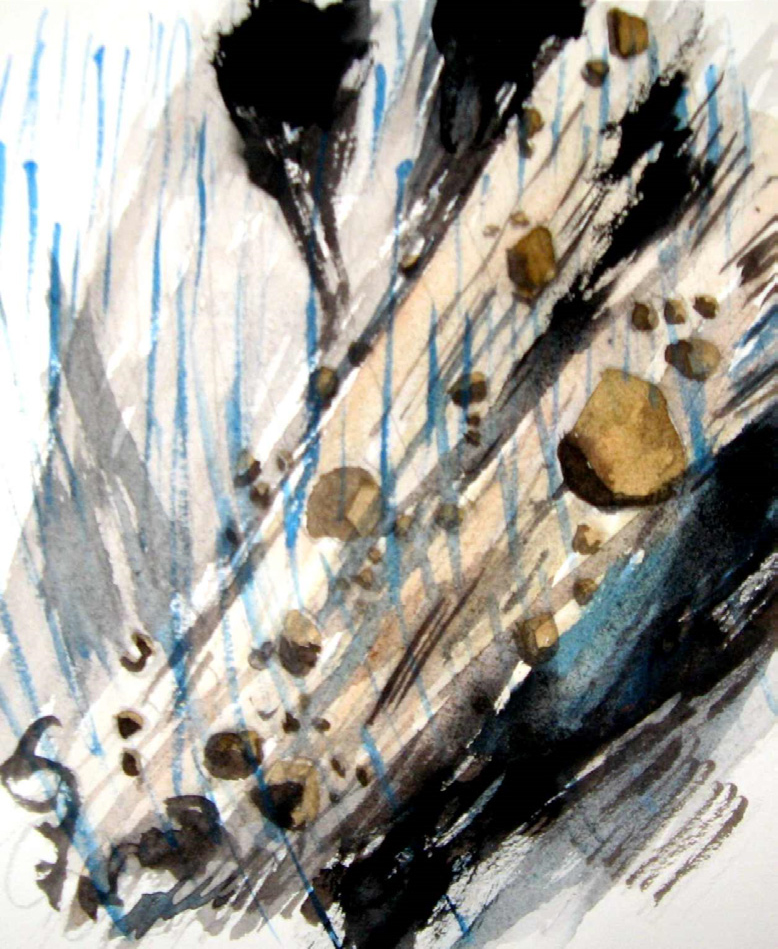
このはげしい雨は、連続三昼夜も小止みなく降り続き、まったく小降りになるような気配は見られなかった。これ以上、雨が続いたら、この猿たちは、他のけものたちといっしょに、食べるものもなく、全滅してしまうかも知れない。娘は、そのことが心配で、心配で、胸がいっぱいになった。
三日目の夜、娘は、「何とかして、けものたちを救うことはできないものか」と、一晩中考えてみたが、とうとう、結論が出ないうちに、夜が明け始めた。
そして、四日目の朝が来た。空を見上げてみても、雨はやみそうになく、湖の水位は、前日よりも、また高くなっていた。
ついに、娘は決心した。
洞穴を出た娘は、はげしい雨をついて、頭からずぶぬれになりながら、湖へ向かってゆっくり歩き出した。そして、湖畔へ着いた娘は、麻のような繊維で織った腰巻き(スカートのようなもの)を脱ぎすて、真っ裸になり、天に向かって、一心に祈り始めた。長い髪は顔や首にまといつき、ふり乱したその髪からは、雨のしずくが滴り落ちている。娘の白い肌からは、ぞっとするほどの恐ろしさが、ただよっていた。

祈りが終わり、娘は、ゆっくりあたりを見まわすと、静かに、濁流渦巻く湖へ、一歩一歩入って行った。はげしい雨が降り続く中、可愛そうに、白い肌は、濁流のために、たちまち汚されてしまった。そして、渦巻く水に、吸い込まれそうな娘のうしろ姿は、あわれであった。
娘は、しだいに深みに入って行く。ついには、渦巻く濁流のために、娘の頭や顔が、見えかくれするほどなってしまった。乙女の生命もこれでおしまいかと思われたその時、娘がニッコリと笑った。
そして、次の瞬間、濁流の上にスクッと立っていた。よく見ると、何と、娘は、下半身がうろこでおおわれ、大きな尾びれが、はっきり見える、人魚になっていたのだ。

人魚は、しばらく、波間から見えかくれしていたが、突然、水面の上に、その下半身と尾を高く垂直に上にあげた。しかし、それもつかの間、人魚は、猿たちの泣き叫ぶ声も聞かないまま、濁流の中に吸いこまれ、再び浮上することはなかった。
と、不思議や不思議。それまで降っていた雨はピタリと止み、風もなくなった。そして淡い太陽の光までも見えるようになった。不思議なことに、天候だけでなく、滝の音が、前に比べて、非常に大きくなったのである。どうやら、滝に異変が起こったようである。
大雨による洪水で、滝の音が大きくなることは分かるが、雨が止んで、三日たっても四日たっても、滝の大きな音はかわらなかった。やがて、湖の水位が下がり、大雨が降る以前の、水位になったが、滝の大きな音は、あいかわらずそのままだった。さらに、湖の水位が、どんどん下がっていく。どうやら、今まで、滝口であった所の破壊が始まったようだ。そして、いったん破壊が始まった滝口は、とどまることを知らなかった。
湖の水位はさらに低くなり、やがて、湖底が陸上にあらわれ始めた。何と、それまで湖の中央で、深いと思われていた所が、予想に反して、砂の台地であったり、岸に運ばれた粘土が、へばりついていたりしていた。人々は、湖底の神秘というものを、思い知らされることになった。そして、幾十年の後、神通川は、滝のない川になってしまったのである。
片掛のこの地に、巨大な滝があったことなど、誰もが信じることができなくなり、いつの頃からか分からないが、「幻の瀧」と呼ばれるようになった。
語り終えた祖母は、小豆の煮え具合を見てくれと、小皿に入れてくれた。 (完)
文山秀三さんの話

祖母の思い出
私には、弟や妹がいて、母が二人の面倒をみていたので、当然のように私は祖母の手で育てられ、いろいろの伝説や物語などを聞く機会に恵まれた。とは言っても、祖母は、平仮名とカタカナを全部知っているだけで、漢字は、画数の少ない字しか知らなかった。しかし、数については、驚くほどの速さで計算していたのを、子供心に不思議に思ったことを覚えている。
その祖母から、ずいぶん、日本古来の話や、おとぎ話などを聞いたが、何度聞いても、正確に話してくれるのにびっくりした。伝説の中に真実が入り、事実の間におとぎ話が入ってくるなど、その話しぶりは見事だった。まだ、幼かった私には、どこまでが伝説で、どこからが真実であるのか判断力がなく、かえって興味深く聞いたものである。
まだ、テレビはもちろん、ラジオもなかったその頃、子供にとっては、いつも家にいて話をしてくれた祖母は、国語の、歴史の、道徳や伝説・おとぎ話などの この上ないよい先生だったのである。
「大昔、わが国に文字がなかった頃、『語り部』がいて、一般民衆に物語や政治のことなどを、言葉を通して知らせた」と聞いていたが、祖母が、時間のたつのも忘れて話してくれる姿は、「語り部」の再来かと錯覚するほどだった。
飛騨街道「片掛の宿」昔語り 『まぼろしの瀧』 文山秀三著