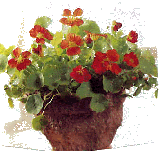夢みる人
治療台に私を座らせてから、その老歯科医は胸に両手を当てて一思案すると、古色蒼然たる電蓄の前へいそいそと、何やらしきりにドーナツ盤のレコードを選んでいる。早春の光が溢れた
小さな診察室に、やがて流れ出た優しいメロディは、昔々の日本の懐かしい流行歌で、思い出
すたびのどかな楽しさがこみ上げる。
「困るなぁ、誰が僕のこと教えたんです?ほんとはこのまま帰ってもらいたいんだけど」と、いき
なり初対面から患者の私に詰問口調で驚かされたのは、未だ予約制も診療拒否とやらもない
よき時代だったから。
「ふむ、男に生れりゃよかったなぁ」 口中を一瞥するなり、連発する言葉がなんだかとても
ユーモラス。いやいや、「性格だけではありません。環境や、知能、教養の程度だって、歯を
一見すればすぐ分かります。」なんて不気味な言葉まで、時々音楽のリズムにつられて大きく
うねる指先をはらはら眺めては、あんぐり口をとられたまま聞くしかない。
明るい午後の日差しの中で、部屋いっぱいに流れるメロディと、白磁の壺に挿されてふるえ
ていた一枝の桃の花びらが、治療の合間に手を止めて、正直に歌に聞きほれている老先生
の仕草とともに、メルヘンの世界にでもいたような。
人は潤いを求めていつの世にも夢みることを忘れない。壮年はたたかい、老年は後悔という
けれど、ゆきつく所医は仙術、といった様子の今は亡い老先生、悠々閑々と大宇宙の一点を
のどかに生きることこそ夢だったのだろう。
「私のことは他の人には言わないでくださいよ、決して誰にも言わないでくださいよ」
安い治療代を払って帰りかける後ろから、何度も念を押されて、掲げられた歯科医院の看板
を思わず横目に見入る背に、陶然と優しい流行歌が流れてた。それは小粋なシャンソンでは
なく、あまいバラードでもなかったけれど、時を経るごとに懐かしく人恋しい思いをつのらせる。
あの時、こんな太いのは見はじめだよ、と老先生が感嘆して、ピンセットの先でピラピラ踊らせ
たピンク色の神経も、すっかり磨り減ってか細く縮んだ×年後の昨今
夢占い
私は一心不乱に見えない山の頂きを目指して登っていた。真紅の絨毯を敷き詰めたタケノコ
状の山は、めまぐるしく足下へ足下へと移動してゆくのだが、わずかな手がかりと足場が確実な
手ごたえで私を導き、ようやく頂上まで登りつめたらしい。と、眼下は一望に開け、洋々たる緑の
大河の流れが目を奪う。突然、後ろからわらわらと人の群れが湧きあがり、エメラルドに輝く飛沫
を素足に散らしながら、私は水上を駆けはじめる。
新緑の樹立ちと、樹漏れ日を思わせる緑と銀の、段だら縞の世界が次々と後ろに消えて
ゆく。 かたわらにぴったり寄り添って走る白い裳裾をなびかせた婦人は誰か分からない。
二人はいつのまにか手を取り合って、無数の鍾乳石が縦横にとび出したような奇怪な洞窟の
中にいた。
あたりは不透明に沈んだトルコ石の青の世界に変わっている、。人声が近づき、二人はまた駆け
はじめる。行く手に白砂かグラニュー糖を思わせる真っ白な渚が続き、見渡す限りの雪原が、
一方は高くそびえる氷の連山が果てしない。いら立ちと不思議な安穏のうちに夢見る私は
駆けながら いつか舞台は皐月闇の中へと暗転するのである。
私はまだ半ば目覚めず、姉が死に至る病床の傍らの無明の闇の中にいて、何かにすがらず
にいれなかったあの頃を思い出す。そしてまた、哀憐と思慕の思いに心の奥まで洗われていた
あの頃を。姉はまだ一度も夢にさえ現れてはくれななかった。
時間と空間を跳び越えて、もう一度夢の世界に戻りたい。あの氷の奇怪なでこぼこは、姉の手
術の傷痕にはびこった不気味な細胞の形態に似ていた。すると、手をとって走った白衣の夫人
は姉ではなかったか−。私はようやく目覚める。そして否応無く姉の死を現実として認めざるを
得ない。
夢は、平素抑圧された衝動や観念が変形し、象徴となって現れるといわれ、ロマン派詩人は
夢を無意識界の啓示として賞賛もするそうだが、フロイトならどう分析するだろう。
姉の生前私は幾度となく、大空を飛翔する夢を見ている。その無限のうちに広がる爽やかさ、
雄大かつ幽玄さは、さめての後もしばし陶然と、妖しい興奮のうちに遊ばずにはいられない。
それは常に人間世界の悲哀や煩雑さを、現実として受けとめ達観し、その呪縛から逃れること
の出来ぬものの、ひと時のはかない慰めにも似ているが。
そして今、何より不思議なことは、あの極彩色の無限曼荼羅の一図絵が、目覚めた瞬間、
いつかどこかで見たような記憶がはっきり残っていることである。